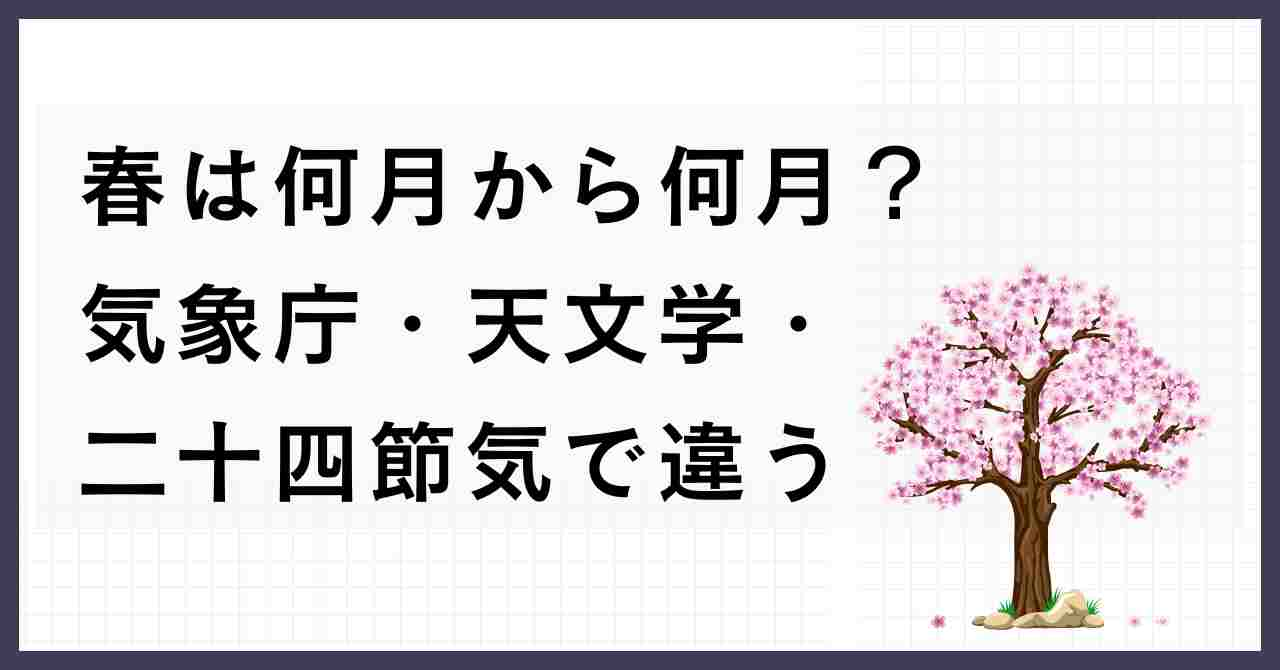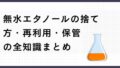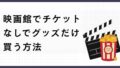「春は何月から何月?」と聞かれて、即答できる人は意外と少ないのではないでしょうか。
実は、日本では春の始まりと終わりを決める明確なルールがひとつではなく、気象庁・天文学・二十四節気といった複数の区分法が存在します。
この記事では、それぞれの区分による春の期間の違いや、春分・立春などを示す「二至二分・四立」の意味をわかりやすく整理します。
季節の変化が見えにくくなった現代だからこそ、自然や暦のリズムに目を向けて「春らしさ」を感じるきっかけにしてみませんか。
春は何月から何月?日本の四季の基本区分
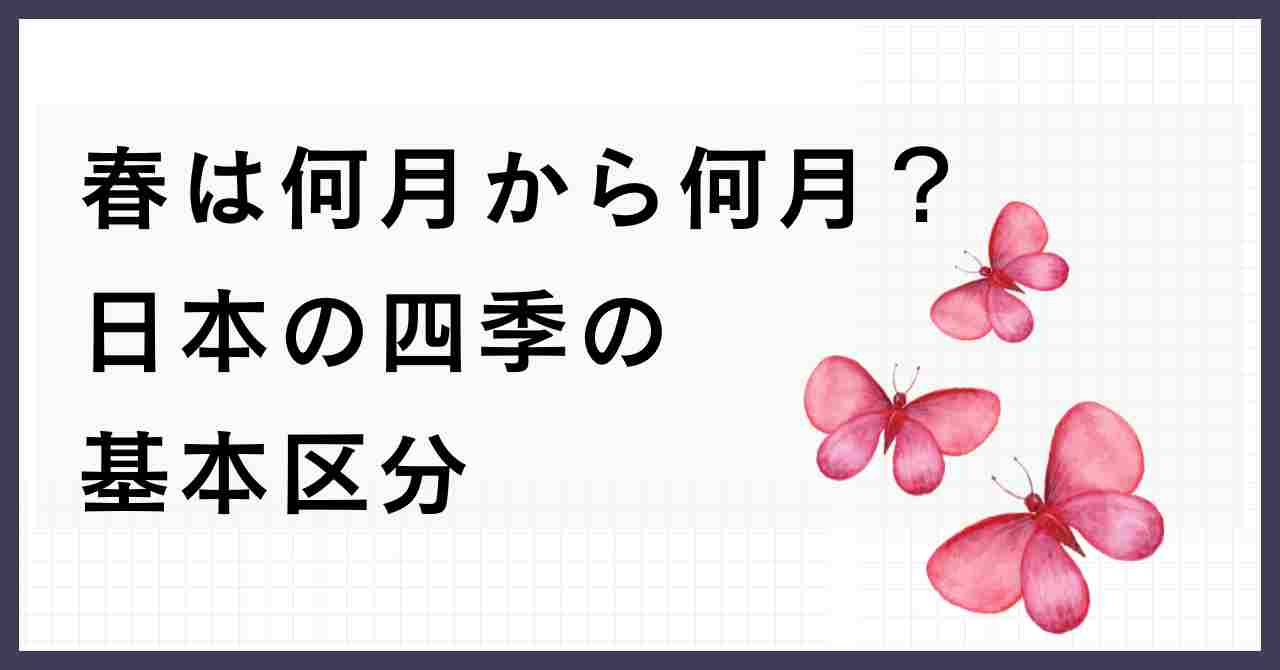
「春っていつからいつまで?」という疑問、意外とすぐには答えづらいですよね。
実は、日本では季節の分け方にいくつかの基準があり、どの暦や観測法を採用するかによって「春の期間」が少しずつ異なります。
ここでは、気象庁・天文学・二十四節気の3つの代表的な区分法をもとに、日本における「春の始まりと終わり」を整理してみましょう。
気象庁による「春」の期間
気象庁では、長年の気象データに基づき、1年を3か月ごとに4つの季節に分けています。
つまり、春は3月から5月とされます。
この区分は気温・降水量・日照時間などの平均値をもとにしており、統計や天気予報でも採用されるもっとも一般的な方法です。
気温の上昇や桜の開花、春一番などの現象が3月ごろから見られることも、この定義にぴったり合っています。
| 季節 | 期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 春 | 3月〜5月 | 気温上昇・花の開花 |
| 夏 | 6月〜8月 | 梅雨・猛暑 |
| 秋 | 9月〜11月 | 紅葉・台風 |
| 冬 | 12月〜2月 | 積雪・寒気 |
衣替えや行事などもこの区分に沿って動いており、私たちの生活に一番なじみのある「春」の基準といえます。
天文学による「春」の定義
天文学的な春は、太陽の動きをもとに決められます。
太陽が黄道上で黄経0度(春分点)に到達した瞬間を「春分」と呼び、その日から次の「夏至」の前日までが春です。
このため、天文学における春の期間は3月20日ごろから6月20日ごろまでと定義されます。
地球の公転による太陽の見かけの位置変化をもとにしているため、自然科学的で国際的にも通用する考え方です。
| 区分 | 基準点 | 春の期間 |
|---|---|---|
| 天文学 | 春分〜夏至前日 | 3月20日頃〜6月20日頃 |
欧米でもこの天文学的な定義が使われており、「春分から始まる春」というのは世界共通の考え方です。
二十四節気で見る「春の始まりと終わり」
最後に紹介するのは、古代中国から伝わった暦の考え方「二十四節気(にじゅうしせっき)」です。
この方法では、季節の始まりを「立春」とし、その前日までを前の季節とします。
つまり、二十四節気では2月4日頃の立春から、5月4日頃の立夏の前日までが春とされます。
| 区分 | 春の始まり | 春の終わり |
|---|---|---|
| 二十四節気 | 立春(2月4日頃) | 立夏の前日(5月4日頃) |
この考え方は「暦の上での春」として今でもよく使われ、年賀状のあいさつ文などで「立春の候」という表現が使われるのもこのためです。
このように、日本における春の期間は、どの区分法を採用するかで1〜2か月ほどの差が生じるのです。
ただし、どの方法にも「太陽の動き」が根底にあり、自然のリズムを感じ取るための知恵であるという点は共通しています。
区分方法によって違う「春」の基準
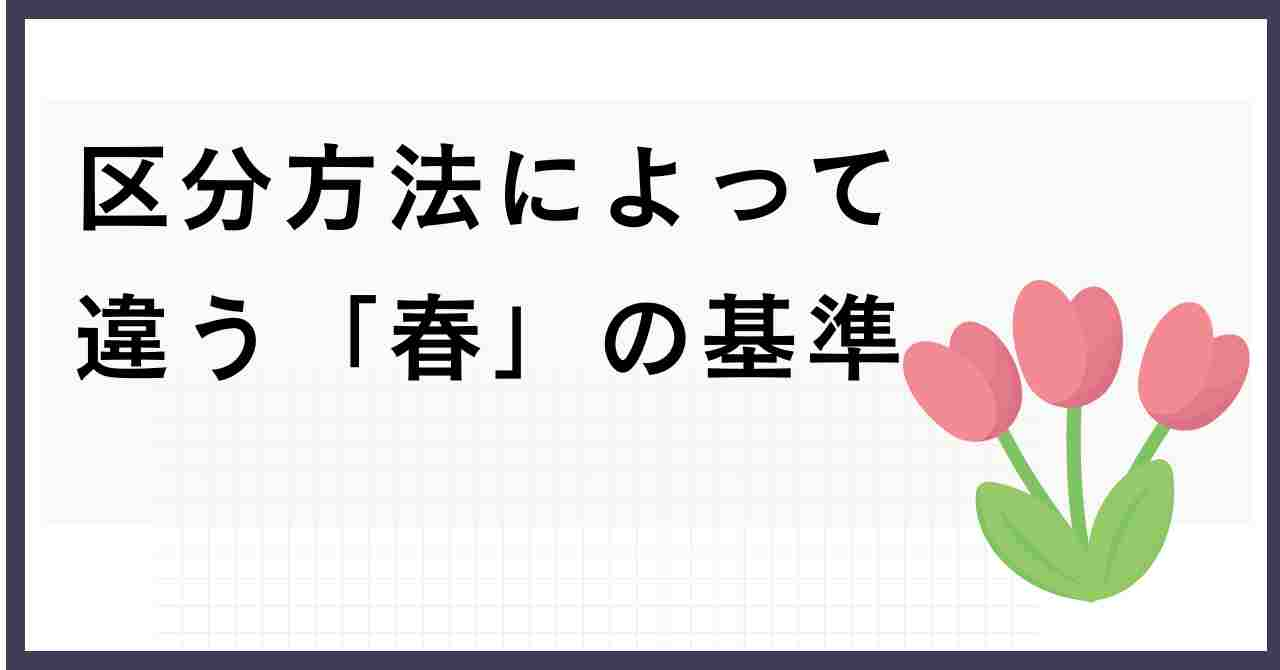
前章では、日本における代表的な3つの区分法を紹介しました。
ここでは、それぞれの方法で「春」がどのように異なるのかを比較し、なぜ複数の基準が存在するのかを見ていきましょう。
気象庁・天文学・二十四節気の比較表
まずは3つの主要な区分法をまとめた表をご覧ください。
| 区分方法 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
|---|---|---|---|---|
| 気象庁 | 3月〜5月 | 6月〜8月 | 9月〜11月 | 12月〜2月 |
| 天文学 | 春分〜夏至前日(3/20頃〜6/20頃) | 夏至〜秋分前日 | 秋分〜冬至前日 | 冬至〜春分前日 |
| 二十四節気 | 立春〜立夏前日(2/4頃〜5/4頃) | 立夏〜立秋前日 | 立秋〜立冬前日 | 立冬〜立春前日 |
このように、どの区分法を用いるかによって、春の始まりと終わりにはおよそ1か月前後の差が生じます。
これは、それぞれの区分が異なる目的や視点で作られたためです。
- 気象庁:観測データに基づいた実務的・統計的な季節区分
- 天文学:太陽の動きに基づく科学的な季節区分
- 二十四節気:農業や生活のリズムを示す伝統的な暦の区分
それぞれの区分には意味があり、どれが「正しい」というものではありません。
むしろ、異なる見方を知ることで、季節を多面的に感じ取る豊かさが生まれるといえるでしょう。
なぜ季節の区切り方が複数あるの?
季節の分け方が複数存在する背景には、人々の暮らしと科学の両面があります。
古代では、農業を中心とした生活において天候の変化を予測することが重要でした。
そのため、二十四節気のように太陽の動きを観察して作られた暦が発達しました。
一方で、近代になって気象観測技術が発達すると、実際の気温や降水量などのデータに基づいた定義が必要になりました。
これが現在の気象庁による区分法につながります。
| 時代背景 | 区分法の特徴 | 目的 |
|---|---|---|
| 古代〜江戸時代 | 二十四節気 | 農作業や生活の指針 |
| 近代〜現代 | 気象庁・天文学 | 観測・統計・科学的理解 |
つまり、暦としての「春」と、体感的・科学的な「春」は少しずつ違っていたのです。
それぞれの時代や目的に合わせて作られた季節の区切りが、今も文化や生活に息づいているのです。
季節の感じ方に正解はなく、自分の暮らしに合う「春の区切り方」を選ぶのも一つの楽しみ方といえるでしょう。
「二至二分・四立」とは?春分と立春の関係
「二至二分・四立」という言葉を聞いたことはありますか。
これは、太陽の動きに基づいて季節の節目を示す暦の考え方で、春や秋の始まりを理解するうえでとても重要な要素です。
ここでは、それぞれの意味と「春分」や「立春」がどのような関係にあるのかを見ていきましょう。
「二至二分」とは何か
「二至二分(にしにぶん)」とは、太陽の高さや昼夜の長さが大きく変化する4つの節目を指します。
具体的には、春分・秋分・夏至・冬至の4日です。
太陽が真東から昇り真西に沈む春分と秋分では、昼と夜の長さがほぼ同じになります。
一方、夏至は一年で最も昼が長く、冬至は最も昼が短い日です。
| 名称 | 時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 春分 | 3月20日頃 | 昼と夜の長さがほぼ等しい |
| 夏至 | 6月21日頃 | 一年で昼が最も長い |
| 秋分 | 9月23日頃 | 昼と夜の長さがほぼ等しい |
| 冬至 | 12月22日頃 | 一年で昼が最も短い |
これらは天文学的な現象に基づくため、毎年の日時がわずかに前後します。
「春分の日」や「秋分の日」が祝日として定められているのも、この二至二分の考えに由来しています。
「四立」とは何か
「四立(しりゅう)」とは、季節の始まりを示す節目です。
具体的には立春・立夏・立秋・立冬の4つを指します。
これらは、二十四節気(にじゅうしせっき)の中でも特に重要な節目で、四季のスタート地点を意味します。
| 名称 | 時期 | 意味 |
|---|---|---|
| 立春 | 2月4日頃 | 暦の上で春の始まり |
| 立夏 | 5月5日頃 | 夏の始まり |
| 立秋 | 8月7日頃 | 秋の始まり |
| 立冬 | 11月7日頃 | 冬の始まり |
たとえば、2月初旬に「暦の上では春」と言われるのは、この立春が基準となっているためです。
実際の体感気温はまだ冬の寒さが残っていますが、暦のうえでは春が始まっているという考え方になります。
「立春」はなぜ春の始まりを意味するのか
「立春」は、二十四節気の中でも特別な位置にあります。
これは、冬至(12月22日頃)を過ぎて太陽が徐々に高く昇り始め、昼の時間が少しずつ長くなっていく時期にあたるからです。
つまり、自然界のリズムとしてはここから春への移り変わりが始まるのです。
立春は「春の兆しを感じ始める日」といえるでしょう。
日本ではこの時期、節分を境に季節の区切りを意識する文化も生まれました。
豆まきや恵方巻などの行事も、立春を新しい一年のスタートとして祝う意味が込められています。
このように、二至二分・四立の考え方は、天文学と文化の両面から季節をとらえる知恵です。
科学的な精度とともに、暮らしの中の感性を形づくってきたものだといえるでしょう。
なぜ春が生まれる?地球と太陽の関係
「春」は、単に気温が上がる季節というだけでなく、地球と太陽の動きが生み出す自然のリズムによって生じています。
ここでは、春が訪れる仕組みを、地球の自転軸や公転の視点から見ていきましょう。
地球の自転軸の傾きと公転の影響
地球は、太陽のまわりを1年かけて公転しています。
その際、地球の自転軸は約23.4度傾いているため、太陽の光が当たる角度が季節によって変化します。
この傾きこそが、春・夏・秋・冬という季節の違いを生み出しているのです。
| 季節 | 地球の位置 | 太陽の高さ(南中高度) |
|---|---|---|
| 春 | 春分点付近 | 中くらい |
| 夏 | 夏至点付近 | 最も高い |
| 秋 | 秋分点付近 | 中くらい |
| 冬 | 冬至点付近 | 最も低い |
地球の北半球が太陽に対して少し傾き始めると、日差しが強くなり昼の時間も伸びていきます。
この時期がちょうど「春」にあたり、温かさを感じるようになる理由です。
南中高度と日照時間の変化
南中高度とは、太陽が1日のうちで最も高く昇るときの角度のことです。
春になると、この角度が冬より高くなるため、地表に届く太陽光の量が増えます。
さらに、昼の時間が少しずつ長くなっていくことで、気温もゆるやかに上昇します。
たとえば、東京の南中高度を比べてみると、次のようになります。
| 節気 | 時期 | 太陽の高さ(おおよそ) |
|---|---|---|
| 冬至 | 12月22日頃 | 約31度 |
| 春分 | 3月20日頃 | 約55度 |
| 夏至 | 6月21日頃 | 約78度 |
このように、太陽の高さと日照時間の変化が、春の暖かさや自然の目覚めを作り出しているのです。
太陽の位置の変化は、私たちの暮らしのリズムや気候にも直接影響を与えています。
春の期間が地域によって異なる理由
「春」とひとことで言っても、日本国内での感じ方には差があります。
これは、緯度や地形の違いによって、太陽の当たり方や気温の変化が異なるためです。
| 地域 | 春の始まり | 特徴 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4月中旬〜5月 | 雪解けとともに春到来 |
| 関東 | 3月中旬〜5月上旬 | 桜の開花で春を実感 |
| 九州 | 2月下旬〜4月 | 早咲きの花が多い |
つまり、天文学的な春は全国共通でも、体感としての春は地域によってズレがあるのです。
そのため、同じ「春」といっても、地域の自然や文化によって違う姿を見せるのが日本の魅力といえます。
地球規模の運動が、私たちの身近な季節感として表れる――そのしくみを知ることで、春の到来をより深く味わえるのではないでしょうか。
日本ならではの「春の感じ方」
春の訪れをどう感じるか――これは単に気温の上昇や花の開花にとどまりません。
日本では、自然や文化、言葉の中に「春」を感じ取る豊かな感性が息づいています。
ここでは、生活や文化、そして日本語に表れる春の表現を見ていきましょう。
桜・花見・行事に見る春の暮らし
日本の春を象徴する存在といえば、やはり桜でしょう。
桜前線が南から北へと移動する様子は、まるで日本全体が少しずつ春色に染まっていくようです。
古くから桜は「春の象徴」として愛され、平安時代にはすでに花見の風習が定着していました。
また、春は新生活のスタートシーズンでもあります。
入学式や入社式、卒業式などがこの時期に重なるのは、春が「はじまり」のイメージを持つからです。
| 行事 | 時期 | 意味・特徴 |
|---|---|---|
| 花見 | 3月下旬〜4月上旬 | 春の風情を楽しむ行事 |
| 卒業式 | 3月 | 別れと旅立ちの節目 |
| 入学式・入社式 | 4月 | 新しい始まりを祝う |
これらの行事が春に集中しているのは、自然のリズムと人の営みが重なり合っているからです。
まさに、日本人の暮らしは季節とともに動いているといえるでしょう。
俳句や季語に見る日本人の春の感性
日本語には、春の情景を表す言葉が数え切れないほどあります。
俳句や短歌の世界では、「季語」と呼ばれる言葉が季節を象徴する役割を持っています。
春の季語には、「桜」「霞」「春雨」「野遊び」などがあり、どれも季節の移ろいを繊細に描きます。
| 季語 | 意味 | 情景イメージ |
|---|---|---|
| 桜 | 春の花の代表 | 淡いピンクと短い命の美しさ |
| 春雨 | やさしい春の雨 | 静けさと芽吹きの季節感 |
| 霞 | 遠景がかすむ現象 | 柔らかい光と幻想的な春の空気 |
このような言葉を使うことで、ただの気候変化ではなく、心の中の春を表現できるのが日本語の美しさです。
春の情緒は、自然だけでなく人の感情にも寄り添って存在しているのです。
現代の気候変化と「春らしさ」の変化
一方、近年では気候変動の影響により、「春らしさ」が少しずつ変わってきています。
冬の寒さが長引いたり、急に初夏のような暑さが訪れたりと、季節の移り変わりが極端になる傾向があります。
桜の開花時期も年によって大きく変動し、30年前と比べて平均で1週間ほど早まっています。
| 年代 | 東京の桜開花日 | 傾向 |
|---|---|---|
| 1980年代 | 3月30日頃 | 安定した時期 |
| 2000年代 | 3月25日頃 | 少し早まる |
| 2020年代 | 3月18日頃 | 早咲き傾向が顕著 |
気候の変化によって、私たちが感じる「春」は以前とは違う形を取りつつあります。
しかし、四季の移ろいを感じようとする心は変わりません。
変わりゆく自然とともに、春の情景を見つける感性を育てていくことが、これからの時代の春の楽しみ方なのかもしれません。
まとめ:春の期間を知ることで、季節をもっと味わう
ここまで、日本における「春は何月から何月か」を、さまざまな視点から見てきました。
気象庁、天文学、二十四節気――どの区分もそれぞれに意味があり、季節の見方を広げてくれます。
最後に、この記事のポイントを整理してみましょう。
季節区分の違いを理解するメリット
まず、春の期間は次のように定義されています。
| 区分方法 | 春の期間 | 特徴 |
|---|---|---|
| 気象庁 | 3月〜5月 | 気温・気候に基づく一般的な定義 |
| 天文学 | 3月20日頃〜6月20日頃 | 太陽の位置に基づく科学的定義 |
| 二十四節気 | 2月4日頃〜5月4日頃 | 暦の上の春・文化的定義 |
つまり、どの基準で見るかによって春のスタートは約1か月ほど変わります。
この違いを知っておくと、暦や行事、自然の変化をより深く理解できるようになります。
たとえば「立春」はまだ寒いのに春の始まりを示す、そんな感覚の理由も納得できるのではないでしょうか。
日々の暮らしに「春の感覚」を取り戻す
現代の生活では、冷暖房や室内空間が整っているため、季節の変化を感じにくくなっています。
しかし、暦を意識したり、自然の変化に目を向けることで、季節を味わう感覚は簡単に取り戻せます。
- 二十四節気をカレンダーに書き込んで意識する
- 散歩中に「春の兆し」を探してみる
- 旬の食材(たけのこ・菜の花など)を味わう
こうした小さな工夫が、日常に季節感を呼び戻してくれます。
春の期間を知ることは、自然と暮らしをつなぐきっかけでもあるのです。
最後にひとつ、季節の区切りに正解はありません。
暦の上でも、科学的にも、そして心の中でも、それぞれの春があります。
あなたが「春だな」と感じる瞬間を大切にすることこそ、季節とともに生きる日本人らしい感性といえるでしょう。